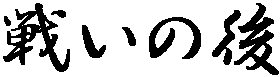
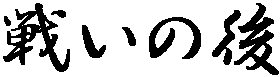
一章 張れない
「入ります」胴は鮮やかな手つきで一枚の札を紙下に忍ばせ、前かがみの上体をゆっくりと起こし目を伏せている。胴の上体は身じろぎもせず心臓の鼓動さえ聞こえてきそうにない。「死んでいるのか?」との想像さえ沸きあがってしまう。
手本引き。悪の華、博打の終着駅とも言えるこの博打。呑む,打つ,買う、ありとあらゆる遊びをこなし、最後に行きつくのがこの遊びである。
静寂が場を包む。その時間は1分であろうか,10分であろうか、いや、ほんの1秒にも満たない時間なのかもしれない。深く重い空気が場全体を覆い包む、傍から見ると異常な光景であろう。
「さあ!入りました」その静寂を破ったのは合力の声であった。先ほどの静とは打って変わって猛々しく、下品とも思える大きな声で2人の強力が声を張り上げる。「さあ!胴前が増えています、皆さんサクサク張ってください!」
その声にテツはハッと我に返った。そうだ、ここが勝負どころなのだ。集中しろ。テツは胴とは対照的に上半身をグッと前屈みにして全神経を胴に集中させた。
この胴は序盤から非常に良いツナ(目)を出し、かなりの金額が胴前に溜まっている。胴前を見る限り、胴はこの勝負で洗う(胴を降りて勝負を止める)つもりであろう。
ここは勝負所である。胴前が少なければ張り子の方も大きく賭ける訳には行かない。胴が受かって(勝って)かなりの金額が溜まっている今が勝負所なのである。モタモタすると胴は洗ってしまい勝ち金をサッサと懐にしまってしまう。そうなっては遅い。繰り返して言おう、ここは勝負所なのである。
テツはジッっとモクを眺めた。4、5、4、1、6、6。前回までの出目である。この胴は2が死に目になっている。中盤に全く出ていなかった2を胴が引きこれが良いツナ(出目)となって、それ以降、胴側の圧勝が続いている。
この胴は受かっている(勝っている)。胴としては勝負に出る理由は何も無い、この回を無難にこなせば、それで洗えば良い。今回はトントンで良いのだ。となると、無難な目とは何か。死に目の2は確かに面白い目だ、しかし、だからこそ逆に狙われる可能性が有る。
無難な目となると4ケン、3ケン辺りだろう。根っ子の6も無くは無い。テツは頭をフル回転させ、目は胴の挙動をじっと観察していた。テツはヤマポンで大に4、中に1、トマリに6を置いた。ヤマポンとは3点張りの変則形で大と開くと3.8倍となり、その他は等倍返しとなる。
そして、手持ちの金を全部置いた・・・いや、置くつもりであった。実際はその行為になかなか移れない。右手に金を握り締めたまま、そこから動けないでいたのだ。
テツの額にはジッと汗が流れ出していた。額だけでない、手の掌も湿っていた。季節は秋である。さわやかな秋風が吹き、決して汗など掻くような気温ではない。
胴に促されてテツはゆっくり札を引いて「見(ケン)します」とか細い声で言った。ほどなく合力の声がかかり勝負が始まった。
胴は目安札の4の札をゆっくりと移動させ、紙下の札を開帳させた。「はい!4です。中も4。無い方は札を引いてください」合力の声が室内に響き渡る。大が開いたものもいるし、全く当たらない者もいた。テツの想像どおり、この目は可も無く不可も無く、胴としてはトントンといったところであろう。
テツの読みは当たっていた。しかし、予想何ぞは誰でも出来る。問題はそこに大金をポンと張れるかどうかなのである。
テツは「ふう」と溜息とも深呼吸とも取れる息をひとつ吐いた。同時に「この辺で洗わさせて頂きます。悪い事をしました」と胴の声が上がった。
二章 博徒へ
テツは地方の上流階級の家庭の次男として生まれた。元々真面目で大人しいタイプで、中学,高校と優秀な成績で卒業して東京の大学に入った。ところが大学に入るとその自由な環境でテツの今まで抑圧されていた物が一気にはじけてしまった。初めは仲間内の麻雀であった。初めこそは負け組にいたテツであったが、元来の凝り性も手伝ってグッと麻雀にのめり込んでしまった。テツが勝ち組に回るのにはそれほどの時間を必要としなかった。
すると今度は仲間内の麻雀では物足りず街のフリーの雀荘に出入りするようになった。レートの方もどんどん大きくなり、大学にも足を運ばなくなった。
街の雀荘やそこで出会った物達と行く賭場では勝ったり負けたりで、結局はトータルで負けていた。すると、親に金をせびって又その金で博打を打ってしまう。
この点が昔のテツの勝ち組に回れない要因であった。負けても何とかなるような状況では崖淵の人間には決して勝てない。博打はある程度の技量に達すると精神力を含めたトータル的な要素での戦いとなる。負けて金で解決できるうちはまだ良い。そうでなくなると面倒なことになる。そう言った点でテツは甘かった。
テツは雀荘だけでなく、チンチロ、丁半、オイチョカブ、バッタマキ等、様々な博打の賭場に顔を出すようになった。そしてほどなく負けて親に金をせびるような生活が続いた。
そんな日々が続いて、テツはついに大学を中退してしまった。この知らせはテツの親元にまで届き、ついに勘当となってしまった。すると、不思議なものでテツは段々と勝ち組に回るようになった。負けると後が無い、博打打にとってタネ(軍資金)がいかに大事なものか、身に染みて感じるようになったのである。
三章 悪の華
博打の要素にレートがある。このレートと言う奴は通常は各人の懐具合で決定されるものであろう。学生のうちは点5の麻雀が社会人になりそれなりの収入を得るようになると、それでは飽き足らずピン、リャンピンとなるものもいるであろう。それ以外にも、各人の技量もレートを決定させる要素となり得る。低いレートで勝ち組になると、博打に費やす努力、才能が勝ち金に見合わなくなってくる。より効率的に勝つにはレートを上げる事である。ただしそこには、方々から勝ち組が集まってきている選抜戦なので、今までのように簡単に勝てるわけでは無い。そうして、レートが上がるにしたがって精鋭が集まり、より密度の濃い戦いとなるのである。
では、その選抜戦のメンバーはこれまでの戦いで大金を掴んだものなのか?ところが、彼らは常に金に窮屈している。勝った所で、次にはさらに一段上の勝負が待っている。真の勝者になるにはすべてのテキをコロシ、博打から身を引いた者だけである。ところがそんな人物はいやしない。ボロボロになるまで戦って、最後は野たれ死ぬだけである。
テツは街の賭場ではすっかり勝ち組であった。或る賭場で一勝負終えたテツにやはり勝ち組であるヒラさんが声をかけてきた。
「よう!テツ。今日も勝ったみたいだな。」
「なんだ、ヒラさんか。悪いがコマ(軍資金)なら廻せないぜ」
「馬鹿にするない。おまえさんにコマ廻してもらうほど落ちぶれちゃいないぜ。それはそうと、おまえさん○○組の賭場は行った事があるかい?」
「いや、話には聞いた事があるが。それで、その賭場がどうした」
「今度、組主催のでっかい賭場が開帳するんだ。おまえさんの腕ならそこそこやれるだろ」
と彼は独特の薄気味悪い笑いを浮かべて言った。
「気味悪いね、ヒラさん。そんなの俺に紹介して。寒い寒い」
「さすがだね、それなら話は早い。おれがスポンサーになるからその金で勝負しないか。儲けは折半」
テツは急に真面目な顔をして、煙草を大きく吸い込んだ。
「それで、種目は」
「ホンビキだ」
テツはホンビキは知ってはいたが手は出した事が無かった。他の博打より、圧倒的に掛け金が大きいこの博打は自分には無縁のものと思っていた。勝ち組に回った昨今でも手を出すとは本人も思っていなかった。しかし、最近は街の賭場では飽き足らなくなってきた。滾(たぎ)らなくなってきたのである。
「良いだろう」 テツは煙草を消して勤めて冷静に言った。
「しかし、折半は取り過ぎだ。六四なら良いぜ」
「まあ良い、それで手を打とう。来週の金曜だ、当日連絡する」
「ああ、待ってる」と言うとテツは外に出た。しかし先ほどとは変わって体中の血液が湧き上がるのを感じた。この感じは何であろう。そうだ、初めて博打を打ったとき、あの高揚感と同じなのだ。
四章 戦いの後
胴は5分のテラ銭を抜いた勝ち金を合力から受け取り、上座から引いた。テツはもう一度大きな溜息をついた。先の4が張れなかった以上今日は恐らくこれ以上は無理であろう。博打は不思議なものでほんの一手の早い遅いが、その日の勝負全てを決めてしまう事も有る。テツもその辺は重々承知している。しかし何故か帰ることが出来なかった。これ以上やっても傷口が広がるのを解っていながら。
これが手本引きが悪の華と言われる所以であろうか。破滅の道に突き進む事が解っていながら、それでいて足を洗う事が出来ない。この博打は例え勝っていても、博打以外の部分がハンチクになり、結局は破滅するのである。
テツはその後も張り続け、最後には文無しになった。明日からはヒラさんのアシ(借金)をツメるために往生しなければならない。それでも体は先ほどまでの勝負で滾っている。そういった自分にハッと気づきテツは苦笑した。
「俺も破滅の道を歩んじまったか。」
外は秋晴れの夜であった。そして月はいつも以上に高く、満月であった。